技術力と職場力で未来を創る!
出光ルブテクノ千葉事業所の組織改革事例(前編)
技術力と職場力で未来を創る!
出光ルブテクノ千葉事業所の組織改革事例
~機能子会社の価値向上に向け実践する組織づくり~
出光ルブテクノは、出光興産株式会社の潤滑油事業を担う機能子会社として、2002年に設立されました。同社は、高機能潤滑油の開発支援、製造、物流、営業サポートなど、多岐にわたる業務を担われています。
千葉事業所では、プロパー社員による事業運営への移行に伴い、専門性を活かした組織運営や独自性の確立が重要な課題となっていました。この課題に対処するための取り組みの一つとして、JMACケイパビリティ研修が導入されました。
今回は、この研修を実施した背景や目的、さらにはこれまでに得られた成果について、同社千葉事業所の責任者の皆様にお話を伺いました。
(計2回に分けてお届けします。今回は前編です)
所在地 〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子一丁目8番地1 川崎室町ビル8階
設立 2002年6月
資本金 1,000万円
従業員 333名(出向社員含む)
インタビュー
出光ルブテクノ株式会社 千葉事業所
事業所長 佐藤 勝正 氏
所長代理 吉井 啓 氏
副所長 兼 テクノリサーチ課長 佐藤 智則 氏
インタビュアー
株式会社日本能率協会コンサルティング
R&Dコンサルティング事業本部
シニア・コンサルタント 塚松 一也

(左から)JMAC 塚松、出光ルブテクノ 長島さん、下妻さん、佐藤所長、吉井所長代理、
佐藤副所長、山本さん、豊田さん

出光ルブテクノ株式会社 千葉事業所 事業所長 佐藤 勝正 氏
2005年1月に出光ルブテクノ株式会社に入社。
国内主要カーメーカーエンジンを用いた潤滑油性能評価試験を担当し、2011年に課長就任。
2014年には工業用潤滑油性能評価部門の課長に就任し、以降2016年に両課実験部門を統括する副所長を
歴任。
2022年4月に千葉事業所長を拝命。現在に至る。

出光ルブテクノ株式会社 千葉事業所 所長代理 吉井 啓 氏
2004年4月に出光ルブテクノ株式会社に入社。
実験部門に配属後、2013年10月~2016年9月に出光興産潤滑油部に出向し、
製品安全(海外化学物質法規制対応など)に従事。
2016年10月に出光ルブテクノ株式会社千葉事業所に帰任後、試験部門の課長、副所長を歴任し、
2023年4月に所長代理として現在に至る。

出光ルブテクノ株式会社 千葉事業所 副所長 兼 テクノリサーチ課長 佐藤 智則 氏
2004年4月に出光ルブテクノ株式会社に入社。
2024年3月まで実験部門にて自動車用及び工業用潤滑油の性能評価試験業務に携わる。
2024年4月より、試験分析、アフターサービス試験業務の試験部門に従事している。

塚松 一也 プロフィール:
JMAC シニア・コンサルタント
R&Dの現場で研究者・技術者集団を対象に、ナレッジマネジメントやプロジェクトマネジメントなどの
改善を支援。変えることに本気なクライアントのセコンドとして、魅力的なありたい姿を真摯に構想し、
現場の組織能力を信じて働きかけ、じっくりと変革を促すコンサルティングスタイルがモットー。
ていねいな説明、わかりやすい資料づくりをこころがけている。
JMAC シニア・コンサルタント 塚松 一也(以下JMAC):
ではまずはじめに貴社の会社紹介をお伺いできますでしょうか。
出光ルブテクノ株式会社 千葉事業所 事業所長 佐藤 勝正 氏(以下 敬称略):
当社は出光興産株式会社の100%出資企業で、2002年6月に設立しました。現在、設立から23年目を迎え、5つの事業所にて事業を展開しています。主な事業内容としましては、潤滑油の製造、物流、営業サポート、そして研究開発などがあり、出光興産の潤滑油事業の一翼を担いながら、共同で事業を運営しております。社員数は現時点で出向社員を含めて約340名です。
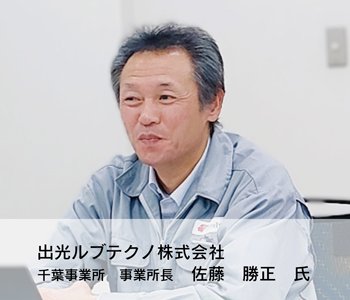
我々千葉事業所では、出光興産営業研究所の敷地内において、潤滑油の研究開発品の試験分析や実能評価試験を中心とした事業運営を展開しております。また、他にも研究品やグリースの製造に加え、敷地内の建屋や設備管理も行っており、これら5つの課の体制で運営し、開発事業が円滑に進むようサポートしています。
さらに、近年では海外R&D部の運営を担当するナショナルスタッフへの試験分析に関する技術指導も行っており、グローバルでの活動が広がりを見せております。特に若手試験担当者の活躍の機会もあり、直接海外に出向き、ナショナルスタッフの方々に試験指導なども行っています。最近では、出光興産営業研究所との連携のもと、海外のR&Dスタッフが来日した際は、試験室での試験指導を行う機会も増えています。そのような中、指導を担当する若手社員たちは、直接英語でやり取りをしながら、試験の指導を行っています。試験室では、同じ試験機や似たような機器を使って試験分析を行うため、精度を一致させることが大切です。このように、出光興産営業研究所の潤滑油開発に貢献しつつ、事業拡大を目指して推進しているところです。
JMAC:
具体的にはどういった国で指導されているのでしょうか。
ルブテクノ 佐藤(勝):
シンガポール、タイ、中国、アメリカ等ですね。先日もナショナルスタッフの方が1週間ほど滞在され、試験分析に関する技術交流の機会がございました。
JMAC:
実機評価試験とは具体的にはどのようなことをされているのでしょうか。
出光ルブテクノ株式会社 千葉事業所 副所長 兼 テクノリサーチ課長 佐藤 智則 氏(以下 敬称略):
実機評価試験は、主に自動車用の潤滑油、例えばエンジンオイルやトランスミッションオイルなど、実際に自動車に使用される潤滑油の性能を評価しています。エンジンオイルに関しては、カーメーカーのエンジンを使用し、実際にエンジンを運転してオイルの耐久性や性能を確認します。トランスミッションオイルについても同様に、試験を行っています。エンジン試験では、ガソリンや軽油を用いたファイアリング実験を行い、燃料を使用しない場合にはモーターを使ったモーターリング試験を実施します。モーターでエンジンを運転し、その際のトルクを計測することも行っています。
また、当社では工業用潤滑油の性能評価試験も行っています。工業系潤滑油は圧延、研削、切削、冷凍機、熱処理、油圧等々、幅広い分野に渡りますが、それぞれ様々な試験を行っています。例えば、油圧作動油は建機用ポンプを用いた耐久試験を実施しています。冷凍機油は空調機に搭載されている圧縮機を用いて耐久試験や潤滑性評価を実施しています。熱処理油は、金属部品を用いた焼入れ実験を実施し、部品の硬度や外観を評価しています。鉄鋼メーカなどで使用されている圧延油や研削油は、実機により圧延、研削性、光沢度などを評価しています。
■JMACの「ケイパビリティ研修」を実施された背景について
JMAC :
今回JMACの「ケイパビリティ研修」を企画された背景について教えてください。
ルブテクノ 佐藤(勝):
まず企画に至った背景ですが、当社の千葉事業所は社員一人ひとりが専門性を持っています。その専門性を社員自ら積極的に活かそうとする姿勢を引き出すためには、きっかけや働きかけが重要でした。そこで、課長級の役職者の指導力を高める絶好の機会として、ケイパビリティ研修を行いました。
また、弊所はプロパー社員のみで運営する事業所であるため、この点を他の事業所に示していく必要もありました。このケイパビリティの取り組みを通し、社員のエンゲージメントを高めると共に、組織の一体感の醸成を目指すのが狙いでした。

出光ルブテクノ株式会社 千葉事業所 所長代理 吉井 啓 氏(以下 敬称略):
当社は設立以来、事業所の運営においては親会社からの出向者がポジションを占めており、プロパー社員はそれに従う形で業務を行ってきました。先ほど所長が申し上げた通り、最近ではプロパー社員だけで事業所の運営を任されるようになってきましたが、それは期待の表れである一方、運営する側が狭い視野に留まってしまうのではないかと危惧していました。親会社から出向された方々は、大企業での多様な経験を持ち、視野が広く豊かな一方で、私たちプロパー社員は主に転職組が中心で、入社後は転勤もほとんどないため、視座や視野が狭くなりがちではないかと感じていたのです。
ルブテクノ 佐藤(智):
課長級の視座を高めることが目的です。これまでにも社内研修や外部の研修・講習がありましたが、どちらかというと定型的な研修が多かったように感じています。その点、今回のJMACの研修は、オーダーメイドのような内容だったと思います。これまでにはない新しい形の研修であり、私たちの事業や視点を新しい方向に向けるきっかけになると期待していました。
■「ケイパビリティ研修」の効果・変化についてお聞きします
JMAC :
では次に、ケイパビリティ研修の効果や参加者の意識、行動の変化について、ご紹介いただけますでしょうか?
ルブテクノ 佐藤(勝):
このケイパビリティ活動を通して、特にリードした課長級以上の役職者の思考や発想に変化が見られるようになったと実感しています。事業所の将来を描くと同時に、社員のエンゲージメントを向上させるために、役職者としての自らの役割について語り合う場ができたことが大きな変化でしょうか。この語り合いの場では、皆が積極的に意見を交換するようになり、課長級以上の人々の意識や行動に顕著な変化が現れてきました。
今後も環境の変化に伴う影響や課題に向き合いつつ、持続的な活動として取り組むことが必要だと思っています。
JMAC :
何か意識や行動に変化があった中で、象徴的な出来事はありますでしょうか?
ルブテクノ 佐藤(勝):
課長級だけで集まり、語り合うことで、自ら考える時間を持つことができたのが特によかった点でしょうか。その結果、彼らが自らの目的や背景を含めて、やるべきことを提案し、それを実行しようとする姿勢が見られるようになりました。このような積極的な提案が増えてきたことが、象徴的な変化だと感じています。
ルブテクノ 佐藤(智):
語り合う場自体は以前からあったのですが、その場で見えるものが今までとは違っていたのだと思います。つまり、今の状況にとどまらず、将来を見据えて考えることができるようになったということでしょうか。もちろん、その中には社員や会社組織のためにどうすべきかという視点があり、さまざまなステージを自分たちで整理して、課題に応じた目標を設定し、議論し合う場を彼ら自身が作り上げていったのだと感じています。
ルブテクノ 佐藤(勝):
まだ完全に見えていない部分もありますが、係長級や課長級の社員たちが実際に活動を行い、その中で出てきた提案の一つに、将来のキャリアパスが見えにくいという課題があり、何をすべきかが見えにくいという声もあったことから、若手社員が上の階層の人たちの苦労話や経験を聞くことで、自分たちのキャリアに置き換えて考えるようになる場面もありました。部下の人たちにとっては、上層部の苦労や将来像を知ることは重要で、その姿勢が見えたことで良い影響を与えたのではないかと思います。また、課長級の人たちがケイパビリティ向上に取り組む姿が社員にとって良い刺激となり、それが社員同士のつながりや成長に繋がったのではないかと感じています。
ルブテクノ 吉井:
私たちの会社は約300人規模なので、課長クラスから会社全体を見渡せる視点が必要だと感じています。課長は自部署の代表として、その部署を良くするために意見を述べるのは当然ですが、会社規模が小さい分、もう少し高い視点で話せるようになることが求められてきました。最近では「課長」の「長」の字に、「超える」という意味の「超」の字を当てて、課を超えて広い視点を持とうということで、実務を任されるような意識が芽生えてきたと感じています。
実際、今年の4月には新任の課長が2名誕生しましたが、彼らは先輩課長たちの活動から影響を受け、業務や管理職としての役割に取り組んでいます。これまでの自分の経験や係長としての仕事とは異なり、幅広い役割に戸惑いながらも、先輩課長たちとの横のつながりを通して悩みを共有し、解決策を模索しています。このような変化が、研修後の今、少しずつ現れてきたと感じています。

ルブテクノ 佐藤(智):
私も課長級同士の横のつながりがより強化されたように思います。以前からつながりはあったものの、さらに深まったと感じています。加えて、研修で学んだことを通じて、将来のビジョンを描くことができたことが大きな変化だと思います。特に、長期的な視点で物事を見ることができるようになったのではないかと。これまでの視野は、目先のことや少し先のことにとどまっていたかもしれませんが、今はもっと先の未来を見据えた思考ができるようになったと実感しています。もちろん、さらなる成長が必要かもしれませんが、その兆しを感じているのは確かですね。
ルブテクノ 吉井:
未来について考える機会を持ったことは本当に良かったですね。単に言われたからやるというものではなく、自分から積極的に取り組むことで部下ともしっかりと話し合うことができたのではないでしょうか。自分がどう考えているかを伝え、意見を交わすことで互いの理解も深まったと感じています。それと、やはり実際に手で書いて形にするという点がとても良かったですね。文字にして、具体的な形にすることで、より明確に自分の考えを整理でき、実際に行動に移しやすくなったと思います。
ルブテクノ 佐藤(勝):
少し余談になりますが、この間、会社の行事でディズニーランドに行ってきました。社員だけでなく家族も一緒に参加できるイベントで、社員は50人程度ですが、家族を含めると80人ほどが参加してくれました。こういったイベントが社員同士の絆を深め、コロナ後もそのつながりが続いているというのは、当社の良い面だと思います。また、社員同士の横のつながりが広がることで、より良い連携が生まれるとよいなと思っています。
